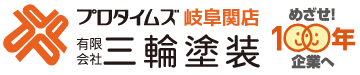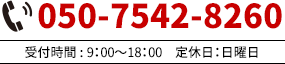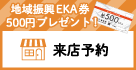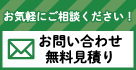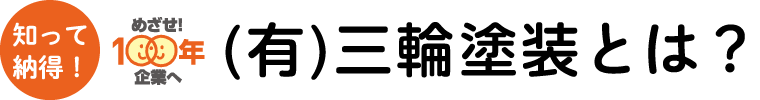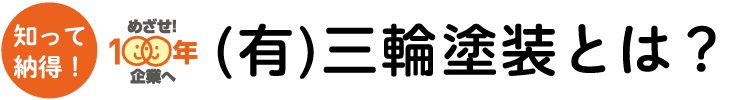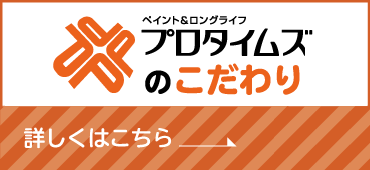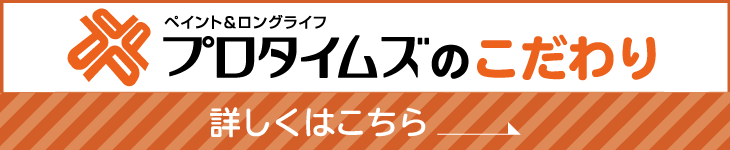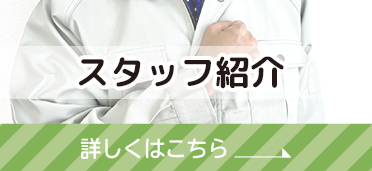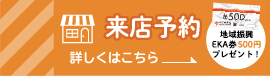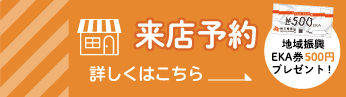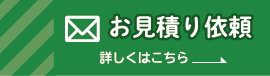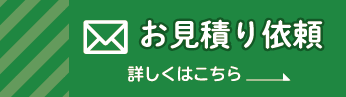2019年3月11日(月)
岐阜県美濃加茂市 外装リフォーム工事 O様邸
みなさんこんにちは。
ここ最近は花粉と日々戦っています。目が痒くクシャミが出て大変です。薬を飲んでマスクしてしっかりと対策をしないと、、、。
気温の方は、日中だいぶ暖かくなり過ごしやすい気温になって来ましたね。
もう春が来ますね。もう冬も終わりです。早いものですね、、、。
さて、余談はこの辺にして本題に入っていきたいと思います。
今回は、美濃加茂市O様邸の工事の続きを紹介していきます。
前回、屋根:外壁の素材と高圧洗浄を紹介しました。
今回は、シーリング工事と養生作業の紹介をしていきたいと思います。
まず、シーリング工事です。
シーリングは外壁のジョイント部分やサッシ廻りに打設してあるゴム材のことです。
シーリングは紫外線には弱くまたシーリングに含まれる可塑剤(柔軟性を与えるために加える)と呼ばれる薬品の寿命によりひび割れや硬化などの劣化が起きます。
ひび割れなどを放置しておくと水が入り小口から水を吸ってしまい外壁の劣化に繋がります。
目地のシーリングは一度撤去し打ち替えを行います。これは既存の上にシーリングを打つと厚みが確保できずすぐにひび割れを起こすためです。せっかく塗装をしてもすぐにひび割れが起きてしまっては意味がありません。
シーリング撤去作業状況です。
続いて、プライマー(接着剤)を塗布していきます。
プライマーはシーリング打設後の接着性などに影響してきますのでとても重要な作業となります。
プライマー塗布作業状況です。
続いて、シーリングを打設していきます。
シーリング打設作業状況です。
続いて、シーリングを均していきます。
厚みを確保しながらきれいに均していきます。
シーリング均し作業状況です。
続いて、養生です。
塗装の養生とは、汚れてはいけない場所や塗らない場所にビニールやブルーシートなどを使い貼っていく作業です。
サッシ廻りと壁の取り合いのラインもこの養生作業できれいに仕上がるか決まります。(腕の見せ所です。)
この作業をきちんと行わないと仕上がったときにきれいに見えません。仕上がってペンキがすごい付いていたりラインが曲がっていたら見っとも無いですからね。細部まで細かく養生していきます。
サッシ廻り養生作業状況です。
土間はブルーシートを使い養生していきます。
ビニールでは歩いているうちに破れてしまうためあまり意味がありません。きちんと隙間が無いよう貼っていきます。
玄関など段差がある場所には目印で目立つテープを貼っていきます。
土間養生作業状況です。
いかがだったでしょうか?
このように塗装工事の前の下準備がとても大切となります。
では、この辺で、、、。