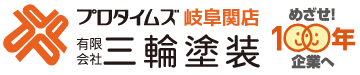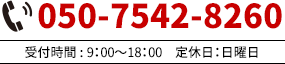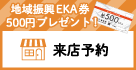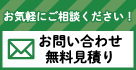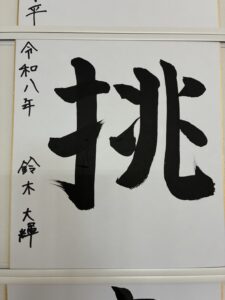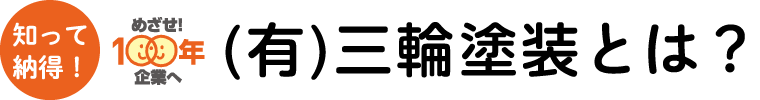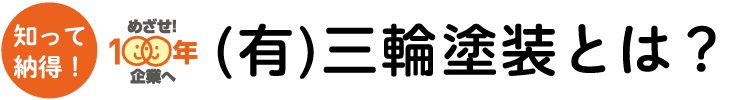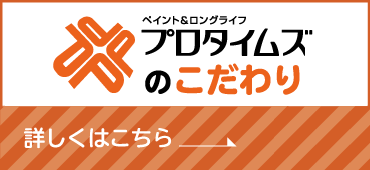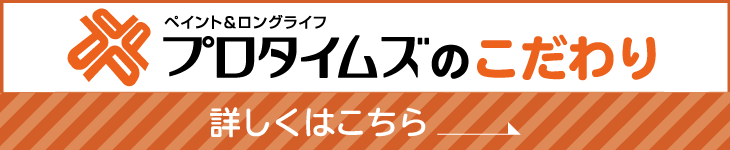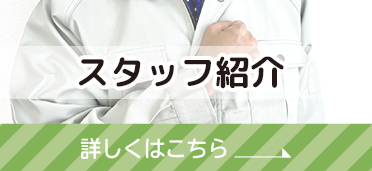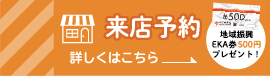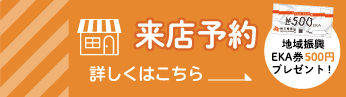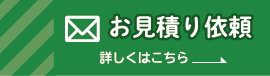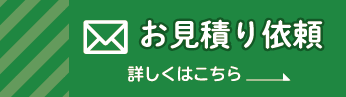2026年2月13日(金)
お客様ともっとつながるために。「LINE活用セミナー」に参加しました!
こんにちは!
本日はセキビズさん主催のセミナー
「ファンを生み出す【LINE活用術セミナー】」に参加させていただきました。
講師は、はなまる経営の山口仁美先生。
とてもパワフルで元気な先生で、あっという間の楽しい時間でした!
セキビズさん、貴重な機会をありがとうございました。
● 本日の学びと気づき
セミナーでは、これからのサービス向上に欠かせないヒントをたくさんいただきました。
✅ 目的を持ったコミュニケーション
「誰に、どのタイミングで、どうアプローチすべきか」の作戦を丁寧に立てることの大切さ。
✅ ご縁を大切にする「リピート顧客」への想い
新規のお客様はもちろん、一度ご縁のあったお客様にいかに喜んでいただけるか。リピートしていただくための工夫が何より重要であること。
✅ LINEという「架け橋」
お問い合わせのハードルを下げ、お客様がより気軽に、便利に私たちを頼れる仕組みを作ること。
今回のセミナーを通じて、あらためて強く感じたことがあります。
それは、「新しくお客様を探し続けること以上に、すでに出会えた目の前のお客様とのご縁をいかに大切にできるか」という視点です。
ビジネスの理屈で言えば「リピーター様を大切にすることが効率的」という側面もありますが、私たちが本当に目指したいのは、単なる効率ではありません。
「困ったときは、またあのお店に相談しよう」
「あそこなら、いつも新しい提案をしてくれる」
そんな風に、お客様の暮らしの一部に寄り添える存在でありたいと思っています。
公式LINEはこちら!
家の劣化状況を見てほしい
塗装・リフォームのことで相談にのってもらいたい
現地調査のお申し込みはこちらからどうぞ
LINEでお友だちになる
お客様にとって「登録してよかった!」と思っていただけるような企画も考えていきます。
どうぞお楽しみに!
常に新しい知識を取り入れ、より質の高いサービスを提供できるよう努めてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。