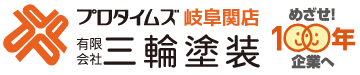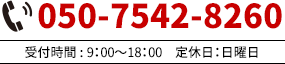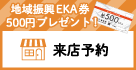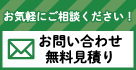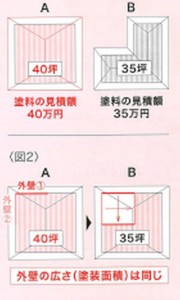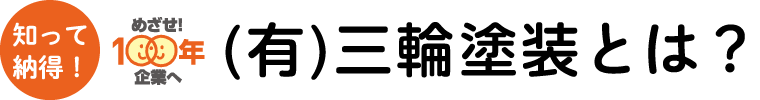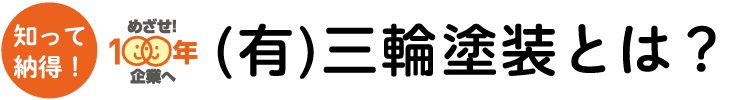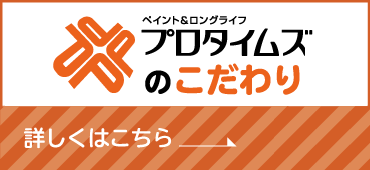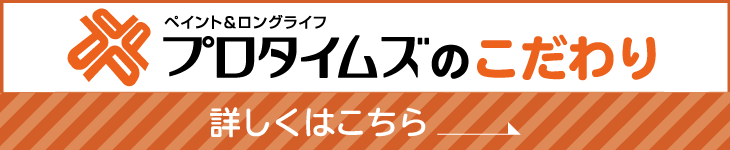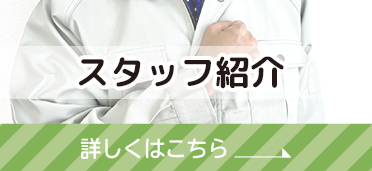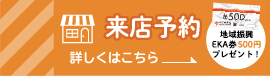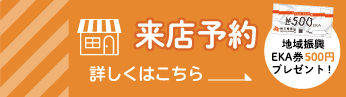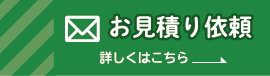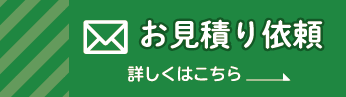2018年5月26日(土)
サイディングボードについて<2>
前回は 「1.サイディングボードの種類」 についてお話ししました。
窯業系、金属系、木質系、樹脂系と4種のサイディングボードがあることが判っていただけたかと思います。
今回はサイディングボードの耐久年数とメンテナンスについて解説していきます。
2.耐久年数
サイディングは大きく4種類あることがわかりました。
ここで気になってくるのが 「何年くらいもつの?」 ということ。
外装材は、美観と防水が目的です。
雨がかかり、紫外線にさらされる外装材は美観という目的では早い段階でメンテナンスしなくてはなりません。
窯業系サディングでは7~10年程度でクリア塗装を行うと、サイディングのツヤ感が戻り、美観を維持できます。
こだわりの外装材を美しい状態で長く保ちたい方は早めのメンテナンスをしましょう。
しかし、防水という目的ではもう少しメンテナンス次期が先延ばしになります。
色あせてきたけれど内部に雨が入らなければ大丈夫という考えなら、メンテナンスを数年先に延ばしても構いません。
下を参考にメンテナンスの計画を立ててみてください。
窯業系サイディング : 7~13年
金属系サイディング : 10~15年
木質系サイディング : 10~20年
樹脂系サイディング : 30年程度
樹脂系サイディングはシーリングを施工しないため、約30年メンテナンスフリーと言っても過言ではありません。
3.メンテナンス
ではメンテナンス時期が来たら、どんなことをすれば良いのでしょうか。
①シーリングのメンテナンス
主に窯業系サイディングや金属系サイディングはシーリングが使用されてます。
このゴム状のシーリング材で細かな隙間を埋め防水するのです。
防水上非常に重要なシーリングですが、紫外線に弱く、早い段階でひび割れや破断が発生します。
こうなると、少しずつ水が建物の中に浸入していくため、シーリングの打ち替えをメンテナンスとして行います。
古いシーリングを撤去し、新たなシーリングを打つ方法です。
状態や場所によっては打ち替えでなく、増し打ちを行うこともあります。
既存のシーリングの上から新しくシーリングを打っていきます。
シーリングは初期の施工や、環境によって劣化の速度が変わってきます。
日当たりのよい南面にシーリングチェックポイントを作っておいて、都度確認すると良いかもしれません。
②塗装によるメンテナンス
窯業系サイディングや金属系サイディングは、工場で塗装された製品を建物に貼っています。
窯業系サイディングにおいては、塗装の膜=塗膜が防水しています。
金属系サイディングでは塗膜によってサビを防いでいます。
この塗膜の成分は樹脂と顔料が分子レベルで結合してできていますが、紫外線による劣化により分解され、顔料が粉のように浮いてきます。
これをチョーキングといい、塗り替えの目安となります。
塗装を行うことで漏水や、サビから守ることができるのです。
③張り替えによるメンテナンス
残念ながら、浴室窓の下や、バルコニーの手すり壁など、部分的に劣化が進行し吸水してボロボロになってしまった窯業系サイディングもあります。
また、サビが進行し穴の開いてしまった金属系サイディングもあります。
こうしたサイディングは塗装を行うことは難しいため、張り替えを行いましょう。
部分的、全体とも張り替えを行うことは可能ですが、部分的に行う際には現状の柄と全く同じものはないということを念頭に置いてください。
張り替えの前には窯業系サイディングが吸水してしまった原因、金属系サイディングのサビが進行してしまって原因を特定し、原因を取り除かないと、貼り替えを行ってもまた同じ現象が起きるので注意しましょう。
④カバー工法による張り替え
何度も塗り替えを行っていたり、劣化が進行しすぎて塗装に耐えうる状態でない場合にはカバー工法を行いましょう。
現状の外壁は撤去せずその上に下地を組み、新たなボードを張っていく工法です。
外壁に密接した給湯器や、エアコン室外機などの移動の必要もあり、規模も費用もかなり大掛かりなメンテナンスとなります。
大まかに4つのメンテナンス方法がありますが、これらのメンテナンスは建物の状態をしっかり把握して行う必要があります。
建物診断を受け、プロに提案をしてもらいましょう。
以上、サイディングボードの 「耐久年数」 と 「メンテナンス」 についてでした。