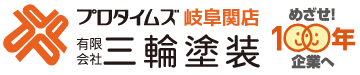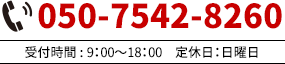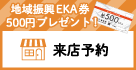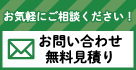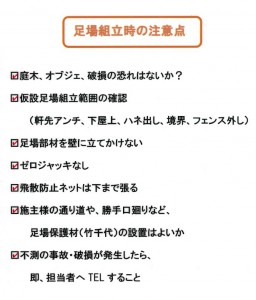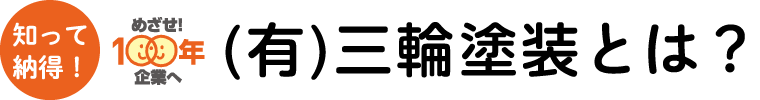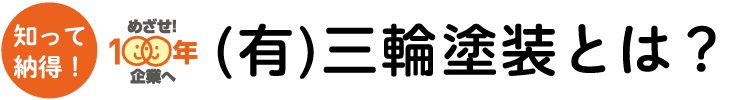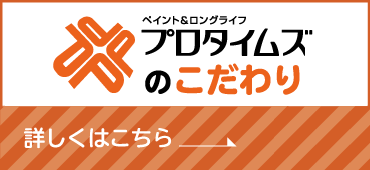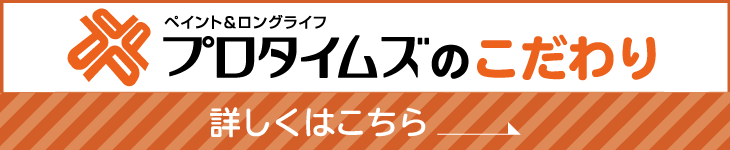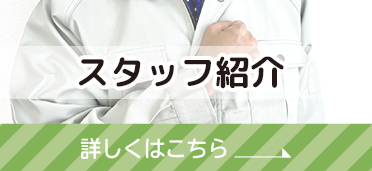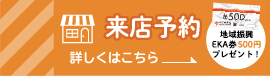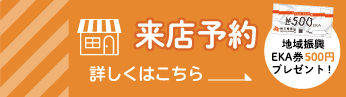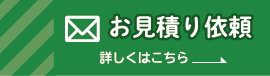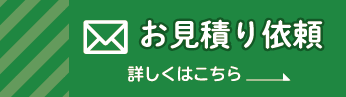2018年7月26日(木)
塗装工事の注意点
皆さんこんにちは。
今回は、塗装工事の注意点を書きたいと思います。
・玄関養生は、床にぴったり固定し、段差には安全トラテープを貼る
玄関はお客様が毎日通る場所です。養生を緩くするとしわが出来、つまずいてしまいます。
土間はブルーシートを使い養生を行うので、段差があるとわかりにくくなってしまいます。そこでトラテープ(黒と黄色)を貼り、わかりやすくします。
・ベランダドレン周りの養生はしない
ベランダのドレンに養生をしてしまうと、雨が降った際水が流れなくベランダに水が溜まってしまいます。
最悪の場合それが原因で漏水してしまいます。ベランダに養生をする際はドレン廻りは切り込みを入れたり、
その部分切ってしまい、ドレンにかぶさらないように注意します。
・ガス給湯器は養生をしない
ガス給湯器を養生して塞いでしまうと、ガスを使用した際、着火不良、異常着火が発生する恐れがあります。
一酸化炭素中毒事故にもつながりかねません。
・エアコン室外機はカバー着用、乗らないエコキュートにも乗らない
現場スタート時の注意点にもありましたが、どんな時もエアコン室外機、エコキュートに乗るとへこんでしまう為乗らないように注意します。
・車両飛散防止シートは必ず2人で行う
工事中お客様の車や近所の方の車がある場合、塗料が付かないように養生をさせて頂いています。
1人で行うとその飛散防止シートで車に傷が付いてしまう恐れがある為、必ず2人で行います。
・近隣に飛散の恐れはないか
風が強かったり、足場の飛散防止養生シートが足りていなかったりすると、近隣の建物や車などに飛散する恐れがあります。
飛散防止養生シートは工事に入る前の確認し、不備があれば再度足場屋さんに来て頂き、完璧にやって頂きます。
風が強い時はその時の状況に応じて、職長が判断し工事を中断します。
・給湯器の電源は抜けていないか
こちらも現場スタート時の注意点にもありましたが、給湯器の電源を確認し使用できる状態かを確認します。
・光ファイバーの線はすぐに切れる
光ファイバー、電気関係の線が建物の至る場所から出ています。
特に光ファイバーの線は細く、すぐに切れてしまいます。
工事の際、塗料が付かないように養生をし完了後に外しますが、
引っ張ったりカッターを使って外すと一緒に切ってしまう恐れがあり注意が必要です。
全ての工事が完了してから電気やインターネット、ガスなどが正常に作動するか確認も行っています。