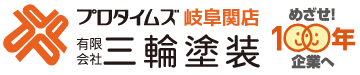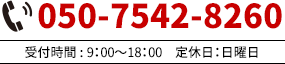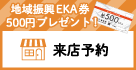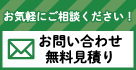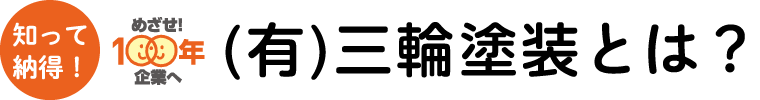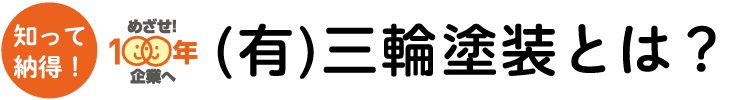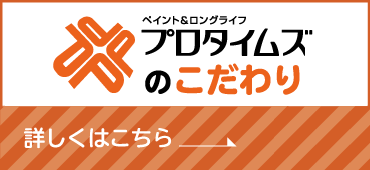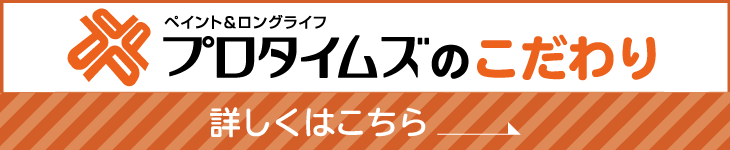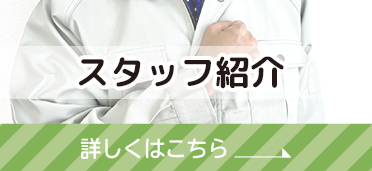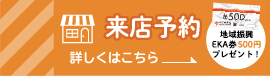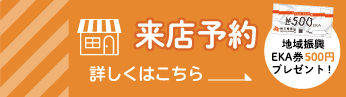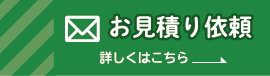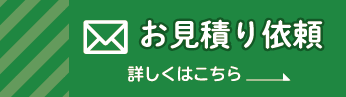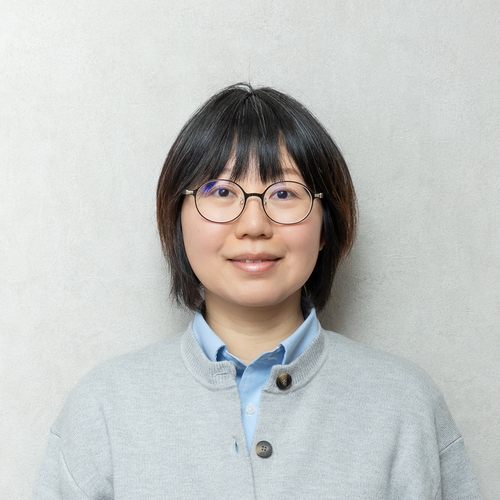 企業のブランディングは“中の人”で勝負する時代?発信のあり方を考える
企業のブランディングは“中の人”で勝負する時代?発信のあり方を考える
2025年7月30日(水)
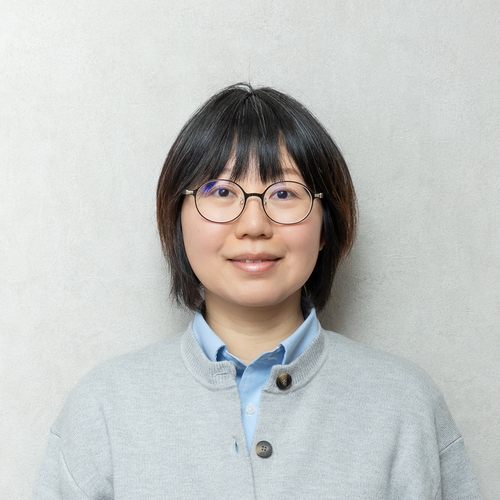
2025年7月30日(水)
📌 この記事の内容
📞 営業電話の内容とは?
ある日、突然かかってきた1本の営業電話。それは「社長に密着して動画を撮り、YouTubeで発信してみませんか?」という提案でした。担当者曰く、最近は中小企業でも“人を見せる発信”が求められており、特に経営者の人柄や仕事への向き合い方が可視化されることで、企業イメージに深みが出るとのことでした。
「プロのカメラマンが1日密着し、動画は編集付きで提供。YouTubeにも最適化した形で納品される」とのこと。さらに、それを通じて“社長や社員の魅力を自然に伝えることで、信頼感や採用力につながります”という説明を受けました。
確かに、近年は会社の規模や知名度よりも、「どんな人がやっているのか」を重視する傾向があります。そういう意味で、今回の営業提案はただの売り込みではなく、企業の本質的な価値を伝えるための“人を軸にしたブランディング”の一手だと感じました。

👀 注目された理由とは?
このような動画が注目される理由は、いくつかあります。
- ▶ 普段は見られない「社長の素顔」が覗ける
- ▶ 密着型のストーリーには、自然と“物語性”が生まれる
- ▶ 社内のリアルな空気感が映り込み、信頼感につながる
- ▶ 視聴者が“人”で会社を選ぶ時代にマッチしている
また、こうした動画は従来の会社紹介や商品PRとは違い、視聴者に「自分ごと」として感じてもらいやすいという強みがあります。「この社長と働いてみたい」「こういうチームの中でならやっていけそう」など、見る人の中に“仮想の体験”が生まれるのです。
特に若い世代は、企業の価値観や人間関係の雰囲気に敏感です。そうした人たちに対して、文章では伝えきれない“温度感”を届ける手段として、このスタイルは非常に有効だと思いました。
💡 プロセスエコノミーとの関係
最近話題の「プロセスエコノミー」とも重なる部分が多いこの企画。プロセスエコノミーとは、完成された商品や成果物ではなく、その裏にある“過程”そのものを公開し、価値として届けるという考え方です。
密着動画では、社長の1日という「プロセス」そのものに焦点を当てることで、その人の価値観や姿勢、社風までを可視化します。「どうやってその結果にたどり着いたのか」「どんなやり取りや判断があったのか」といった“過程”を見せることで、企業の信頼性や誠実さが伝わります。
ただし、プロセスエコノミーが双方向・参加型であるのに対し、この動画スタイルは完成した編集コンテンツであるという違いもあります。言い換えれば、「プロセスを第三者視点で再構成して見せるエンタメ型プロセスエコノミー」と捉えるのが近いかもしれません。
🤔 やるべきか、やらざるべきか
このような動画企画に惹かれる一方で、慎重に考えるべき点も多くあります。
- ・社長や社員の“素の姿”をどこまで見せてよいか
- ・撮影によって現場の空気感が変わってしまわないか
- ・動画が“やらせっぽく”見えた場合、逆効果にならないか
- ・編集や構成にどれだけ関われるか(出来上がりのコントロール)
- ・制作費や継続発信のハードルは高くないか
とはいえ、「動画が完成するまでやらない理由を考えていたら、いつまで経っても変わらない」という現実もあります。だからこそ、“一歩踏み出して試してみる価値”はあると感じました。
🎬 塗装会社に合った動画企画とは?
いきなり密着動画を制作するのが難しい場合でも、自社で段階的に取り組める方法はたくさんあります。以下は、塗装業ならではの現実的な動画アイデアです。
- ▶ 職人の1日密着(朝の準備~作業工程~片付けまで)
- ▶ 営業担当のご提案同行(色選び・見積説明・お客様とのやり取り)
- ▶ 新人の“できるようになったこと”ドキュメント(成長の記録)
- ▶ お客様との色選び密着(シミュレーション・実物比較・最終決断)
- ▶ 社内イベントの裏側(朝礼・誕生日会・安全大会など)
- ▶ 実際に寄せられた口コミを読み上げて紹介(感謝の言葉とともに)
こうした動画を“作り込まずに、淡々と映す”だけでも、十分なリアリティと共感が得られます。演出よりも“そのままの空気”を伝える方が、かえって魅力的なのです。
また、YouTubeだけでなくInstagramやTikTokに短縮版を出すことで、若年層への認知・採用にもつながります。
🔚 まとめ
「社長に密着してみませんか?」という一本の営業電話。
それは、単なる売り込みではなく、“企業の中の人の魅力をどう伝えるか”という本質的な問いを投げかけられたように思いました。
人を見て会社を選ぶ時代。だからこそ、見せるべきは商品や価格ではなく、「誰がどんな想いでやっているか」なのかもしれません。
私たち自身も、自社の魅力を“現場のリアル”から伝えていく準備を、少しずつ始めてみてもよいのではないでしょうか。