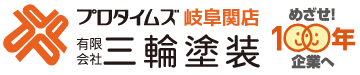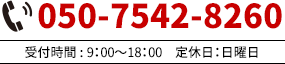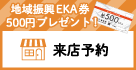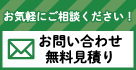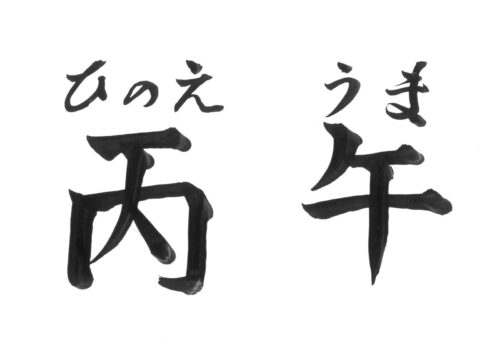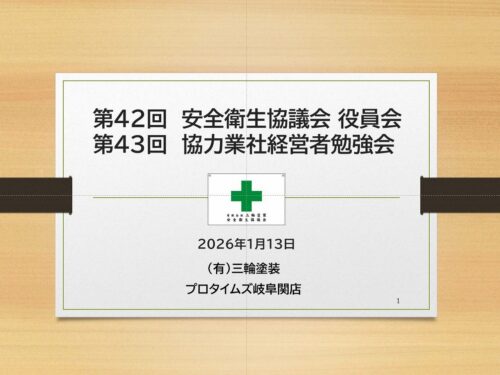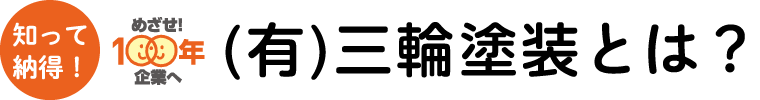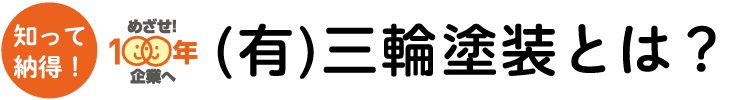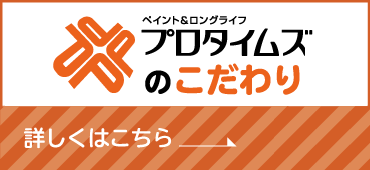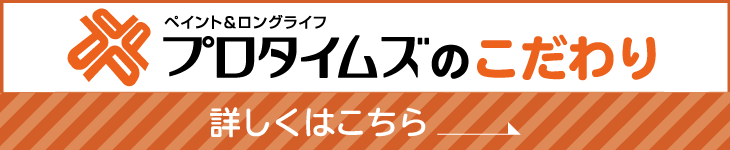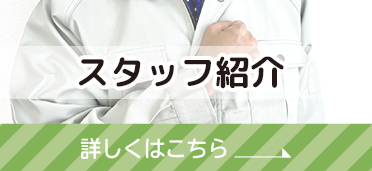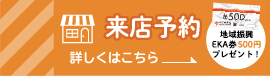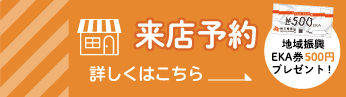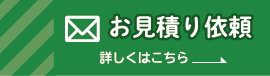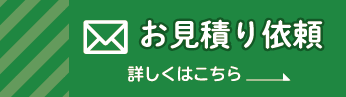2026年1月17日(土)
豊かな人生にするために、若いうちから継続して取り組んだ方がいいこと3つ
いつも仲良くして頂いている同業社長が語っていた話。
彼は社員さん、また残念ながら転職することになった方にも
言ってる言葉があるんだそうです。
「豊かな人生にするために、若いうちから継続して取り組んだ方がいいこと3つ」
本を読むこと
歯を大事にすること
足腰を鍛えること
これは本当に納得です。
そして、個人的には
④ 食事と“食べ方”をコントロールすること
もぜひ加えたい。
結局のところ、身体こそが最大の資本。
仕事も人生も、体がなければ成り立たない。
さらに言えば、健全な精神は、健全な身体に宿る。
派手さはないけれど、若いうちからコツコツ積み上げた人ほど、
年齢を重ねたときに差が出る分野だと思います。
長く充実した人生を送るために、心身ともの健康は本当に大事ですね。
どうか皆様もご自身を労わってくださいませ。