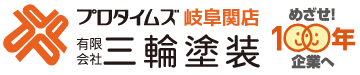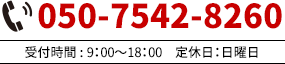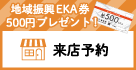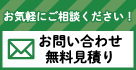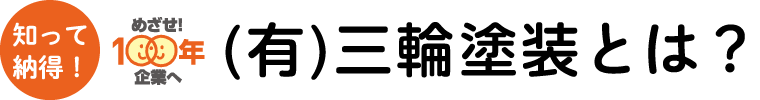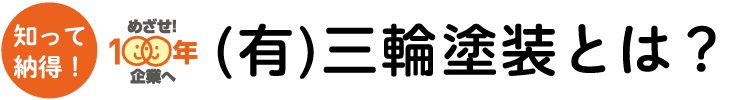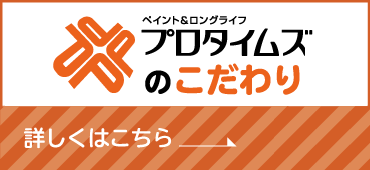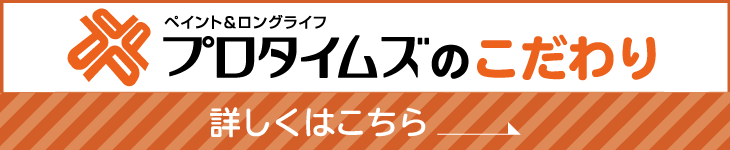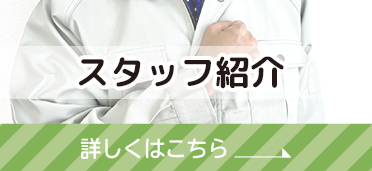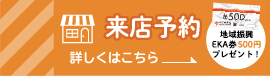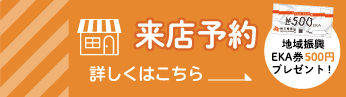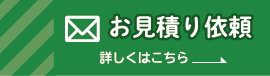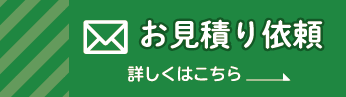丈夫な粘土瓦屋根でもメンテナンスが必要です。
丈夫な粘土瓦屋根でもメンテナンスが必要です。
2023年8月24日(木)

2023年8月24日(木)
営業の三室です。
本日は和風住宅に使われることの多い粘土瓦について紹介します。
粘土瓦って何?という方でも、写真を見ればピンと来るはず。

日本人には馴染み深い瓦ですよね。
こうした粘土瓦は粘土を釜で焼いて製造されています。強い衝撃を与えない限り、その寿命は半永久的です。
そのため、塗装などのメンテナンスも不要になります。
また、不燃材料であるため耐火性にも優れており、断熱性、遮音性に優れています。
日本の気温や風土に合っている為、日本家屋には見た目も機能もマッチしています。
さらに細かい話をすれば、粘土瓦の中にも、いぶし瓦・釉薬瓦・無釉薬瓦と種類があります。
いぶし瓦

釉薬瓦
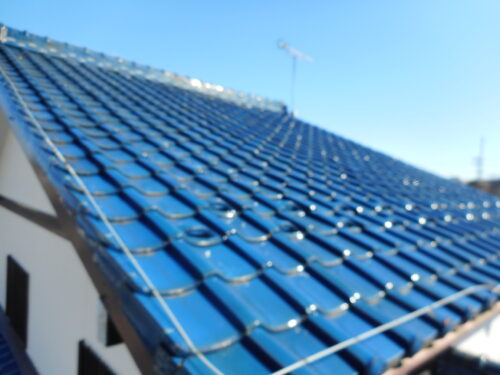
無釉薬瓦

さて、今回はそんな粘土瓦のメンテナンスについて紹介させていただきます。
上記のように非常に耐久性に優れた粘土瓦は、割れやズレがない限りは問題ありません。
しかし、ノーメンテナンスではなく、瓦屋根を構成する下地や漆喰などの建材はメンテナンスが必要です。
なかでも、劣化しやすく適度なタイミングで補修しなければならないのが「棟」です。


棟とは屋根の頂点部分もしくは屋根の面が付き合わさった部分をいいます。
ここから雨水が入らないように棟瓦が設置されていますが、経年によってずれたり破損することがあります。
棟の劣化として1番多いのが漆喰の劣化になります。


漆喰には、棟に雨水を侵入させないことと、美観を保つという役割があります。
瓦屋根では、粘土などを土台として瓦を積み重ね、棟瓦を固定しています。

棟の内部にあり、冠瓦やのし瓦を支えるために設けられているのが葺き土です。
はじめは、泥状で水分を含む葺き土ですが、劣化により痩せて硬くなると瓦の固定力が弱くなり、ズレや歪みの引き金となってしまいます。
葺き土に雨水の影響がないように守るのが漆喰です。
漆喰の初期劣化として見られるのが、ひび割れやコケの発生です。


そこからさらに劣化が進行すると、漆喰の剥がれが起きます。

この状態からさらに劣化が進むと、棟内部に雨水が浸入し始め、
葺き土の固定力を弱らせることで、棟の歪みやズレが起きたり、雨漏りをする可能性があります。
それでは、棟の改修工事を2つ紹介します。
①棟積み直し工事
こちらは、棟を一度解体し、再施工する工事です。
棟の歪みやズレ、または中の葺き土が流れ出てしまっている場合にお勧めの工事です。
まずは、棟を解体していきます。




瓦を一度撤去しながら、葺き土や漆喰を全て撤去処分していきます。
そして、新たにセメント漆喰を敷き詰めていきます。
瓦の勾配や高さを調整しながら、既存の瓦を使用し、棟を積み直します。




②漆喰塗り替え工事
こちらは、古くなった漆喰を取り除いた後、新しい漆喰を塗り込む工事です。
漆喰の劣化症状が比較的軽く、棟へのダメージが深刻ではない場合、漆喰塗り替え工事での補修が可能です。
まずは、既存の漆喰を撤去します。


次に、漆喰の密着性を上げるために、プライマーを塗布します。


最後に新たな漆喰を塗り直し、完了です。


三輪塗装では、屋根の劣化症状に合わせて工事をご提案しております。
お家の気になることは、是非三輪塗装までお問い合わせを!